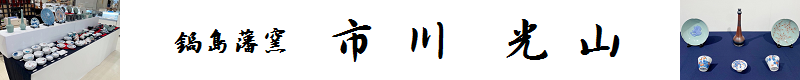
2025年4月23日(水)
4/14 西日本新聞社から取材の依頼があり、本日4/23(水)の新聞に掲載されましたので御報告します。
これからも地域のために頑張っていきたいと思います。

鍋島焼「開窯350年」伝統受け継ぐ秘窯の里
さいこう大川内山 鍋島焼350年
献上の品を生産していた江戸の世にある一日のような、特別で日常的な作業が続いていた。
伊万里市南部の大川内山地区にある鍋島焼の窯元「光山窯」の作業場。窯主の十九代市川光山さん(64)は、自らのろくろ仕事で成形した大型の酒器「瓶子」を左手で支えながら、大量の呉須を含んだ太い「だみ筆」を素早く丁寧に操り、色を塗り込んでいった。
分業制が確立された現代の陶磁器業界。市川さんは42歳までに「ろくろ成形」「下絵」「上絵」の3部門すべてで伝統工芸士と1級技能士になった。2019年には「現代の名工」の表彰も受けた。卓越した技は伊万里・有田地区の職人でも唯一無二の存在だ。
「ちょっと内側を触ってみませんか」
促され、恐る恐る瓶子の口から指を入れると、曲面が美しい表側と異なり、かすかな凹凸を感じた。
「この微妙な段差が人の手だけで成形した証し」と市川さん。複雑な作品の場合、何点かのパーツに分けて結合させるか、用意した型に陶土を流し込んで固める鋳込みが主流という。「ろくろ1つでこうした瓶子を作ることができる人は、もうほとんどいない」。誇らしさに加え、どこか寂しさも感じられた。
◎最高峰を支える卓越の技◎
江戸時代、当代一の陶磁器を将軍家などに献上するため最高峰の技術者だけを集めて作られた鍋島焼。職人は「御細工人」などとして藩から禄をもらい、名字帯刀も許された。有田の民窯に腕利きの評判を聞けば、職人の入れ替えも行われたとされる。
明治維新で藩窯がなくなった後も市川家は家業として作陶を続け、鍋島焼の伝統を重んじる気風も引き継いだ。男5人、女2人のきょうだいで自身は末弟。兄たち4人と同じく幼い頃から家業を手伝い、父の十八代光山さんからは「陶芸に不要な筋肉がつく」と運動を禁じられた。
「3回駄目だしを受けると見限られ、父に『野球をやってもいいよ』と言われる。兄たちは一人また一人と抜けていった」。努力と才能がともに求められる厳しい環境。「窯主として上に立つ以上、全て作業が職人よりできて当たり前。早めに見切りを付けるころも優しさだった」と、親心にも思いを寄せる。
その父は20歳の時に他界。すでに伝えられるべき技術は習得し、覚悟も固まっていた。自らを高めていく道のりを進む中、師と仰いだのは「ろくろの名手」とされ、全国伝統工芸士会会長も務めた中村清六さん(故人)だった。
「大正生まれの本当に厳しい人。自分の作品を大切にする心を学んだし、時には刃物を額近くにあてられ、ぶれない体、ろくろに向き合う姿勢の大切さを教わったことも。まさに“真剣”だった」と懐かしむ。
◎ ◎
江戸時代終わりごろの大川内山を描いた県指定重要文化財「染付鍋島藩窯絵図大皿」(県立博物館蔵)には、ほぼ中央に瓦ぶきの大きな建物が描かれている。
周囲に連なる小さなかやぶき屋根とは一線を画し、細部まで書き込まれたこの一軒は、鍋島焼の成形や絵付けが行われていた「御細工場」とされる。
現在の光山窯の作業場はこの御細工場跡に建つ。基礎部分は、大皿にある石垣が今も使われている。「ここから最高の陶磁器を生み出すことこそ、鍋島焼の歴史の継承であり私の運命」と市川さんは言う。
自宅そばでは、イチョウの大木が若葉を揺らしていた。推定樹齢250年で高さ30m。大皿には対となる雄株も描かれているが、実物はすでに伐採された。
作業の合間など、ふとした瞬間にこの大木が目に留まる。「見た目には分からなくても毎年確実に年輪を重ねている。奇をてらわず、前に進むだけ。目指すのは鍋島の正常進化」。孤高の存在になったイチョウの木に自身の姿を映し見る。
〇 〇
秘窯の里で育まれ、日本陶磁器最高峰の歴史と技をつないできた鍋島焼。「開窯350年」で注目を集める今、大川内山に根を張り伝統を担う窯人たち、魅力にひかれ、エールを送る人たちに焦点を当てる。(糸山信が担当します)
*左上写真:自らろくろで成形した瓶子に、だみ筆で下絵付けを施す十九代市川光山さん
Copyright © Ichikawa Kozan. All Rights Reserved.